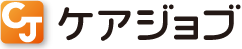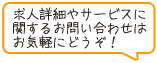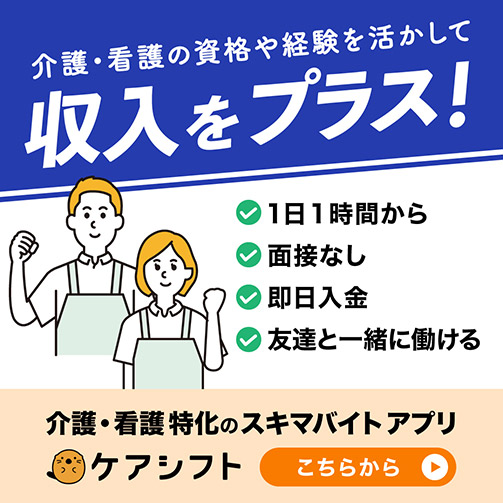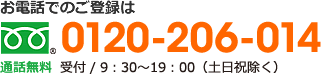No.279 介護士として押さえておきたい現場用語:信頼されるために

介護の現場では、日常的に多くの専門用語が飛び交っています。介護職に就いたばかりの方や、これから介護の仕事を目指す方にとって、これらの用語は最初の壁に感じるかもしれません。しかし、現場で使われる言葉を正しく理解することで、ケアの質は向上し、利用者との信頼関係やスタッフ間の連携もスムーズになります。本記事では、介護士として知っておくべき代表的な用語を目的別に分けて紹介し、現場での具体的な使い方や背景を丁寧に解説します。
日常業務でよく使われる基本用語を理解する

介護の現場では、「ADL」という言葉が頻繁に使われます。これは「日常生活動作」のことで、食事・排泄・入浴・更衣・移動といった基本的な生活動作のことを指します。ADLの評価は、利用者の自立度や介護の必要性を判断する基準となるため、理解しておくことが重要です。
また、「IADL」という用語もあります。これは買い物や調理、掃除、金銭管理など、より高度な生活動作を表し、在宅生活の継続に関わる重要な指標です。これらの用語は、介護計画や記録作成時にも頻繁に登場するため、早い段階で習得しておくと現場での対応力が高まります。
ケア内容や観察時に用いられる専門用語

観察記録や申し送り時には、身体の状態や行動に関する用語も多く使われます。たとえば「バイタルサイン(VS)」は、体温・脈拍・呼吸・血圧など、生命維持に関わる基本的な指標の総称です。これらの数値を定期的に確認することは、体調変化の早期発見につながり、重大な事故や疾患を未然に防ぐためにも欠かせません。
さらに、「褥瘡(じょくそう)」という用語も介護現場ではよく登場します。これは長時間の圧迫によって皮膚や筋肉が壊死する「床ずれ」のことです。褥瘡予防のためには、定期的な体位変換や皮膚観察が必要であり、その記録にも正しい用語の使用が求められます。
介護保険制度に関する用語を押さえる
介護職は、単にケアを提供するだけでなく、介護保険制度を理解し、適切なサービス提供につなげる役割も担います。そのため、「要介護度」「ケアプラン」といった制度に関する用語の理解も欠かせません。
「要介護度」とは、介護保険を利用するための認定基準で、要支援1・2、要介護1~5の7段階に分かれています。介護度が上がるほど支援の必要性が高いことを意味し、サービスの内容や回数、費用負担に影響します。「ケアプラン」は、利用者一人ひとりの生活状況や希望に応じて作成される介護計画で、ケアマネジャーが中心となって作成します。