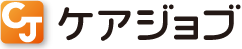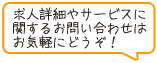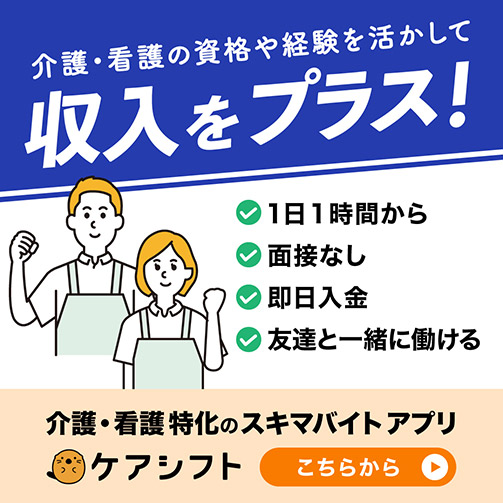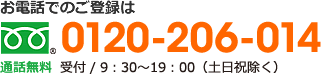No.277 介護士が知っておきたいリハビリの基本と実践のポイント

介護現場において「リハビリ」は、利用者の生活機能を支える重要なケアのひとつです。理学療法士や作業療法士が主導する専門的な訓練が中心となる一方で、日常生活をともに支える介護士にもリハビリ的視点が求められています。実際、介護士が関わる日々の動作の中にも、リハビリにつながる工夫や声かけが無数に存在しています。本記事では、介護士が現場で活かせる「リハビリの基本的な知識」と「実践におけるポイント」を丁寧に解説し、利用者の自立支援とQOL向上に役立つヒントをお届けします。
リハビリは「特別な訓練」だけじゃない

「リハビリ」と聞くと、平行棒やバランスボールを使ったトレーニングを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、介護現場におけるリハビリは、日常生活動作(ADL)を支える“生活に根ざしたリハビリ”が主軸になります。
たとえば、ベッドからの起き上がり、食事の際の姿勢保持、トイレまでの歩行など、日々の「当たり前」の行動こそがリハビリの機会です。利用者ができることを奪わず、ほんの少しのサポートで「自分でやった」と感じてもらえるよう工夫することが、介護士に求められるリハビリ支援の第一歩です。
理学療法士(PT)や作業療法士(OT)との連携を通じて、利用者の状態に応じたリハビリの方針や動作方法を確認し、日々のケアの中で実践できるかを意識していくことが大切です。
介護士が担う「生活リハビリ」の役割とは?

介護士にとってのリハビリ支援は、「見守る・引き出す・続ける」という3つの役割に集約されます。まず「見守る」とは、利用者の動きや意欲をよく観察し、どこまで自分でできているのか、どのような工夫で支えられるかを理解することです。
「引き出す」では、利用者の力を信じ、できることをあえて任せてみるという関わりが重要になります。たとえば、着替えを手伝う際に「どこまで自分でやってみましょうか?」と声をかけたり、歩行補助の場面で「あと一歩ですね」と励ますことで、利用者自身の意欲や残存能力を引き出すことができます。
最後に「続ける」。リハビリは一度やれば終わりではなく、継続的な働きかけによって成果が生まれます。日々の繰り返しの中で、介護士が「昨日よりも少しできたこと」を共に喜び、積み重ねていくことが生活機能の維持・向上につながります。
リハビリ的視点を活かす日常の声かけと工夫
介護士の「ちょっとした声かけ」や「動線の工夫」は、リハビリ効果を高めるうえで非常に大きな意味を持ちます。たとえば、移乗のときに「右足を少し前に出してから立ってみましょう」と伝えるだけで、スムーズに動けるケースもあります。また、歩行訓練中に「この先の椅子まで一緒に歩いてみましょう」と具体的な目標を提示することで、利用者のモチベーションを引き出すことができます。
環境面では、手すりの設置や段差の解消、椅子の高さの調整なども“リハビリ的配慮”のひとつ。安全を確保しながら、利用者ができる限り自分の力で動けるような空間づくりを意識することで、無理のない範囲での活動量を増やすことができます。
こうした「現場でできるリハビリ支援」を積み重ねていくことが、利用者の自立心と尊厳を守るケアにつながります。